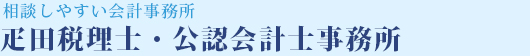会社設立、起業・開業する創業者の成長をサポート。気軽に相談できる若い税理士をお探しなら、浜松の税理士法人Compathy(コンパシー)にお任せください。
受付時間 | 8:30~17:30 |
|---|
アクセス | 助信駅より北に徒歩5分 |
|---|
相続税の申告・相続対策
相続対策ってどんなものがあるの?
相続対策と聞いて何をイメージされるでしょうか。このようなお話をすると、どうしても節税対策だけをイメージされる方が非常に多いように思います。
しかし、相続対策には節税対策だけでなく主に3つ、①節税対策、②納税資金対策、③遺産分割協議対策の3つになります。どれも重要ですが、会社経営と同じで、節税対策を意識しすぎて他の大切なことがおろそかになってしまったり、節税にはなったけど、お金は結局なくなってしまったということが起きてしまうことがあります。
このようなことはないようにしたいものです。
そのためにも、我々税理士事務所や司法書士・行政書士の先生に早い段階から相談し、節税対策をしながら納税資金をどのように確保していくか相談をしたり、遺言書作成をすることで遺産分割でもめることがないように対策をしていただくと良いと思います。このように専門家に相談をしていく過程で、どのような財産がどれだけあるか考えることにつながりますし、さらに深く入ると税金がどれくらい払うことになるか考えることになったり、相続が発生する前に売却をおこなったりするなど対策が可能になります。
疋田税理士事務所に相続で相談に来ている方をみていると、平均寿命が延びるとともに、少子化が進んでいるためか、子供がもともといなかったり、子供が親よりも若くしてなくなるケースがあります。
子供がいない場合には、相続はどうなるか?
浜松の疋田税理士事務所はこちらをクリック
- 配偶者と尊属
- 尊属がいない場合は配偶者と兄弟姉妹
- 兄弟姉妹がない場合はその子どもたち
以上の者が相続人となります。
この場合、当然に配偶者のものになるだろうという認識でいるためか、遺言状が作成されていないケースが多くあります。
一緒にすんでいる不動産の名義がなくなられた方の名義でしたらどうでしょうか。それ以外の夫婦で築いた財産のほとんどの名義がなくなられた方の名義でしたらどうでしょうか。
遺言状がない場合で、配偶者が夫婦で築いた財産なので自分が相続したいと考えても、配偶者の兄弟姉妹等の配偶者以外の相続人の同意が得られないということが起こりえますし、実際に起こっているのです。
配偶者が相続するための手続き
遺産分割協議書等の書面に署名および実印での押印並びに印鑑証明書の交付です。
実際にこれらのことをお願いすることを想像してみてください。
署名および実印での押印、印鑑証明書の交付をお願いしやすい人とは仲が良いが、お願いしにくい人とは疎遠ということです。
そのようなことを、配偶者にさせるのでしょうか。
配偶者にさせないようにするために、相互に財産のすべてを一方の配偶者に相続させる旨の公正証書遺言で遺言状を作るのがよいです。
また、司法書士や行政書士に相談をするのがよいと思います。遺言状をつくったけど、それで本当にいいのか心配になるよりも専門家の協力を得て、問題が起こるおそれがないという心理的安心感を得るのが良いです。
子供がいないケースで説明をしましたが、配偶者が相続を行ったとして、次のどのような問題・注意点が考えられるでしょうか。
- 直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。(兄弟姉妹の相続権は、1代に限り代襲相続します)
- 兄弟姉妹もいなければ、相続人が存在しないケースとなります。
兄弟姉妹が相続人になるケース
兄弟姉妹でも、おそらくお世話になった方がいるのではないでしょうか。いらっしゃればその方に残すように遺言状を作成することが望ましいです。
相続人が存在しないケース
相続人の存在が明らかでない場合、相続人が存在しな場合は、本当にいないか捜索する手続きが必要になります。相続人はいるが、行く不明という場合はこのケースにはなりませんので注意してください。
また、この相続人を捜索した結果、相続人が現れなければそれに応じて手続きが必要になります。
手続きの流れ
- 相続人が存在しないか、明らかでないときは、被相続人の死亡時に相続財産は法人となります。
- 利害関係者、検察官等の請求によって相続財産管理人の選任を申し立てます。
- 家庭裁判所はその申し立てを受けて、相続財産管理人が選任されたことを2ヶ月間公告します。(この間、相続財産管理人が相続財産の保存・管理を行います。)
- 公告後、2ヶ月経過しても相続人が現れなければ、管理人は債権者や受遺者に対して2ヶ月以上の期間を定めて債券の申し出を行うように公告を行います。
(債権者や受遺者から申し出があれば、清算をします。) - 債権の申し出期間が終了して相続人が誰も申し出なかった場合、相続財産管理人又は検察官の請求により、6ヶ月以上の期間を定めて相続人があればその権利を主張すべきことを公告します。
- 6ヶ月以上の公告期間が経過しても相続人が現れないとき、また現れても相続が承認されないときは相続人の不存在が確定します。
相続人の不存在が確定してからの手続き
相続人の不存在が確定すると国庫への帰属するのではと考えられる方もいらっしゃるでしょうが、まだ帰属はしません。
最終の相続人捜索公告の期間が満了した後、ここから3ヶ月は特別縁故者による相続財産分与の申立てが認められています。特別縁故者については後ほど説明しますが、申立てがなかった場合や分与がなされても残余財産がある場合には、相続財産は国庫に帰属し、相続財産法人は消滅することになります。
特別縁故者への財産分与制度
相続人が不存在の場合、かつては国庫に帰属させていたのですが、国庫帰属させるより相続人と特別の縁故があった人に財産を分与した方がよい場合もあるとして昭和37年の民法一部改正によって創設されたのが特別縁故者への財産分与の制度です。
特別縁故者の範囲
民法は、特別縁故者を、以下のように規定しています。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養監護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故のあった者
どのような人が具体的に特別縁故者として取り扱われるかというのは裁判所の裁量にゆだねられています。
特別縁故者は、相続人を捜索するための期間満了後3ヶ月以内に、相続開始地の家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)に対して申し立てを行います。
詳しくは、司法書士等の専門家にご相談ください。
疋田会計事務所では、司法書士等の専門家の紹介も行っております。
税理士/浜松市中区/相続税の申告/相続手続/疋田会計事務所/浜松
相続人がいないケース【相続人以外の人が分与を受けた場合】浜松市中区/税理士事務所
相続人がいない場合には、基礎控除は5,000万円のみとなります。
(※なお、この点については平成23年の税制改正で3,000万円とされる案が提出されていますので改正動向に注意してください。)
取得財産は、相続財産法人から遺贈により取得したという取り扱いになり、財産分与をされた人が相続税の申告を行わなければなりませんので注意してください。
ここで、相続税の申告というと、申告期限を心配される方がいらっしゃるかもしれませんが、財産を取得した時期は分与が確定した時となりますので、そのタイミングから10ヶ月が相続税の申告期限となりますのでご安心ください。
なお、相続人がいないケースでは、取得者が配偶者、一親等の血族以外となることから相続税が2割加算となります。
相続人がいないケースの手続きは、司法書士と税理士セットでお願いすると安心です
税理士/相続税/疋田会計事務所(浜松中区)トップページ
確定申告書を提出する義務のある人が死亡した場合にも、当然のことながら死亡するまでの所得というのがあるため、確定申告の手続きをしなければなりません。(それを準確定申告といいます。)
ここで、申告をする本人が生存中には、ご本人が3月15日までに、前年の1月1日から12月31日までの所得の申告をすることになります。
ただ、準確定申告のケースでは、申告をする人はなくなっているわけですし、12月31日に死亡するとは限らないため以下のような問題があります。
- だれが準確定申告をするか?(申告する人の問題)
- いつまでに申告すればいいのか?(申告期限の問題)
- どこに申告をすればいいのか?(申告地の問題)
様々なケースを想定して説明をしたいと思います。
1.年の途中で死亡した場合
これが、もっともわかりやすいケースになります。
年の途中で死亡した場合には、以下のようになります。
- 死亡した人のその年の1月1日から死亡の日までの所得
- その相続人が行う。
- 相続の開始があったことを知った日(死亡の日)の翌日から4ヶ月以内に行う。
- 死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出する。
2.申告期限前に死亡した場合
次に死亡するタイミングが1月1日から12月31日の期間ではなく、翌年の1月1日から3月15日までの申告期限までにその申告書を提出しないで死亡した場合にはどう取り扱うかがあります。
- その相続人が行う。
- 相続の開始があったことを知った日(死亡の日)の翌日から4ヶ月以内に行う。
- 死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出する。
3.相続人が2人以上いる場合
いままでは、その相続人が行うという形で説明をしてきました。ここで、当然のことながら思うのは、相続人が2人以上いる場合の準確定申告は、どのようにして申告をするかということになります。
- 原則として、各相続人が連署して1通の準確定申告書を提出しなければなりません。
- 例外として、他の相続人の氏名を付記して各相続人が別々に準確定申告をすることもできます。
この場合には、直ちに他の相続人へ申告書に記載した内容を通知しなければならないことになっています。 - 相続人が2人以上いる場合には、各相続人は、相続分によりあん分して計算した額を納付することになります。
4.相続を放棄した人がいる場合
その相続人のうちに相続放棄をした人がいる場合には、どのようになるでしょうか。その者も申告は提出するのでしょうか。
- その相続放棄者以外の相続人が準確定申告書を提出することになります。
(その相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。)
5.指定相続分が確定していない場合
準確定申告の納付税額は、法定相続分または遺言による指定相続分がある場合には指定相続分によりあん分して計算した額となります。
しかし、その遺言について争いがあるため各相続人の指定相続分が確定しない場合があります。
このような場合には、法廷相続分によりあん分した税額を各相続人が納付することになります。遺言についての争いが解決した結果の相続分が法定相続分と異なることになった場合でも、法定相続分による準確定申告は訂正する必要はありません。
※死亡した場合で、たとえば、税理士にお願いせず確定申告を行っていたケースがあると思います。そのような場合には、申告になれていない者が行うことになるので難しいです。
税理士等に相談するのが良いと考えられます。
税理士/浜松市中区/相続税の申告/相続手続/疋田会計事務所/浜松
同族関係の個人・法人間の土地賃貸借取引—相当の地代を収受

被相続人が同族関係者となっている同族会社が、被相続人所有の土地を借りていて、相当の地代を払っている場合には、同族会社の株式を評価するときに、その土地の自用地としての価額の20%に相当する金額を借地権の価額として純資産価額に計上します。
また、土地を賃貸借していて、「土地の無償返還の届出書」を提出している場合もこれと同様の取扱となります。
(通常、無償返還の届出を提出しているときは、借地権の評価はゼロとなるのですが、同族会社の場合はこのようになります。そのほか、無償返還の届出を出していてもその貸借が使用貸借である場合には、土地は自用地価額となる点に注意が必要です。)
それでは、この同族会社が被相続人から借りている土地の上に立っている建物を貸家としている場合にはどのようになるでしょうか。
そのような場合、当該同族会社の株式の評価上、純資産価額に計上する借地権の価額は、自用地価額×20%(借地権割合)×(1−借家権割合)というように自用地の借地権価額から借家人の敷地利用相当額を控除することになります。
この点にも注意しましょう。
相続の財産評価は、注意点が沢山あります。
会社の顧問税理士など税理士に相談されることをお勧めいたします。
会社の貸借対照表に役員借入金があるという会社も最近の不景気のためあるのではないでしょうか。それも高齢になった役員からの役員借入金が多額にあるという場合もあるかもしれません。
その際に、仮に役員が亡くなられたときには、「貸付金」として相続財産の中に入ってきます。
しかも、小規模宅地の特例のように評価が引き下げられることはなく、預金などと同じようにそのままの金額で計上されてしまいます。
税制改正などにより、相続税の控除額が引き下げられる可能性も高いですから、法人の役員借入金(役員の貸付金)については、できるだけ早期に解消するのが良いと考えられます。
例えば債務超過になっている場合には、債務免除を行うことも考えられるでしょう。
この場合には、相続税法基本通達9-2のいわゆる「跳ね返り贈与」に注意をする必要があります。つまり、同族会社で株主から債務免除を受けたときに、他の株主の株価が上昇した場合には当該金額について贈与を受けたものとみなされるものです。
当然のことながら、債務免除を行う際には、その合理的な理由が当然あるでしょう。単に、「もう返してもらわなくていい」ということは現実的にはありえず、裏になんらかの理由があるはずです。その理由と行為によっては課税を受けるということです。
債務超過が長く続いて、なかなか返してもらえそうにないため債務超過を解消させる水準まで債務免除を行うということであれば、当該理由を書面により明らかにさせた上で債務免除を行ってください。
債務免除や債権放棄は、債権者の一方的かつ不要式の行為(民法519)とされており、客観的はわかりにくいものです。公正証書等公証力があるものでなければならないというわけではありませんが、どの程度の金額が放棄したのかを書類により明らかにしてください。
※債務免除についてのみ説明をしましたが、相続税を考慮して役員借入金を減らす場合には、報酬の代わりに役員借入金の返済を優先することなども考えられます。
どのような方法がよいかは、単に税務的側面だけを重視して考えるのではなく、自社の経営のことも含めて検討を行い、当該判断に基づき手続き・処理を行う際には帳簿上のみで処理を行うのではなく、書面の作成をすることが、税務の証拠ということだけでなく、後日、紛争等が生じないようにするためにも必要と考えられます。
税理士/浜松市中区/相続税の申告/相続手続/疋田会計事務所/浜松
相続税の課税が強化される方向となっていることから、贈与税額控除の110万円は使用しないともったいないことについて説明をしました。
それならばということで、不動産について110万円ずつ贈与するということを考えられるでしょう。
土地の贈与を行う
土地を贈与するには、持分贈与と分筆贈与の二つの方法があります。持分贈与か分筆贈与かということであれば、費用の点からは持分贈与がよくなります。なぜなら、分筆の場合には、分筆するための費用がかかります。
では、持分の贈与にして、契約書上で持分を贈与していくことを考えると思います。しかし、公正証書によって行ったとしても移転登記がなされたときに贈与を行ったとみなす判決があります(名古屋高裁平成10年12月25日判決)。
また、これ以外に考えそうなこととして、110万円を毎年贈与するのは時間がかかるから、特定の子供に1つの土地を毎年110万円ずつ持分を移すのではなく、子供3人なら3人に110万円ずつ贈与することを考える人がいます。
しかし、共有はあとからもめる恐れがあるのでおすすめしません。
その他の注意点
- 農地の贈与は手間がかかります。
- 不動産取得税や登記の費用負担が相続のケースと比較して贈与の方が高くなっています。
※ですから、土地について110万円ずつ贈与するというのは私はあまりおススメしません。
相続については、お客様の考えと税理士の考えややり方というのが重要となります。どれが正解かというのはお客様の判断や価値観で異なることもあります。是非、専門家と時間をかけて相談しつつ進めていただければと思います。
浜松/税理士/浜松市中区の疋田会計事務所/相続・事業承継支援
毎年110万円の基礎控除の枠を使って贈与することをお勧めしました。
そこで、110万円ずつ贈与をしよう、そして合計でたとえば1,100万円を贈与したいので、10年間贈与しようとする人もいらっしゃるかもしれません。
しかしこの場合に注意しなければならないことがあります。
それは、税務当局から連年贈与については、最初の年に1,100万円の贈与することは決まっていて、あとは履行するだけだと見られてしまう恐れがあることです。
そこでよく言われる方法として下記のように行うことが提案されます。
- 贈与する金額を毎年変更すること
- 110万円を少し意図的に超えさせて贈与税を納めること
ともかく、毎年贈与する金額については意思決定を行って、それについての証拠を残すことに注意して欲しいです。
(証拠を残すとなると公正証書し、なおかつ現金ではなく銀行で振り込むことなどが考えられますが、たとえば毎月9万円振り込むのは面倒だから自動で振り込むようにすることは避けた方がよいことはいうまでもないでしょう)
浜松市/相続税・事業承継/疋田税理士・会計事務所/トップページ
小規模宅地の特例の適用【相続税の申告・相続税対策】
浜松市/疋田会計事務所
小規模宅地の特例という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
これは、自宅の土地や会社の土地、賃貸を行っている土地などについて、50%の減額又は80%の減額が認められる制度です。(面積に制限はあります。)
この減額の割合を書くだけで効果の大きさはわかっていただけると思います。
小規模宅地の特例は2009年までとそれ以降とでは大きく変わり、その適用要件が厳格化されるようになりました。
それでも、要件が厳しくなっただけで、要件をみたせば減額されることは変わらず、いまだにその影響は大きいものです。
相続税の課税が強化され、今までは自営業者がほとんどであった相続税の対象が、一般のサラリーマンの人でさえも相続税の申告を行う人が増えてくると思います。
その際に財産評価をどのように行うかにより税金額は大きく異なります。
相続税の申告については、税理士にご相談ください。
浜松/相続税・事業承継対策/浜松市中区の疋田税理士・会計事務所トップページ
相続税の納税者の割合が少ないことから、相続税の基礎控除の水準を引き下げるられることになりました。
基礎控除が現行の水準になったのは、バブル期に不動産の価格が上昇したことに配慮し水準を高めてきた結果です。(相続税制の様々な控除はこの側面がほとんどなのです。)
となると、現在の土地の地下が下落している面からしても、控除を引き下げるというのは当然のながれなのかもしれません。
(ただ、事業を行っている人が保有している自社株式だけでかなりの金額になるところもあるので、それには何らかの対応が必要な気がします。)
現行 | 改正後 | |
|---|---|---|
定額控除 | 5,000万円 | 3,000万円 |
法定相続人比例分 | 1,000万円×法定相続人 | 600万円×法定相続人 |
つまり、六割になったと覚えておいてください。
対処方法
この結果、今まで以上に、生前に贈与を行うなどの対応が必要と考えられます。
これから10年のうちに、多くの中小企業が会社の経営権つまり社長の交代を行うでしょう。
しかし、それから株式を移すなどを行うのでは、限界があることが多いと思います。
今回の改正を機に自社の事業承継について一度ご家族で話し合われることを強くお勧め致します。
なお、この改正については適用について継続審議となり、平成23年度からの適用はなくなりました。
浜松市中区/疋田税理士・公認会計士事務所/浜松での事業承継・相続税対策/トップページ
「よく贈与税は高いです」というお話を聞きます。だから、贈与はしたくない、贈与をするとしても年に110万円までと考えられる方が多いです。
それと同時に相続税は払いたくないと考えられる方も多いです。
財産の金額がどれくらいあるかということと、準備期間によってはこのようなことも可能かもしれません。
しかし、あまりに税金を払わないことばかり考えすぎるとかえって相続で税金を多額に納めることになることもありますので注意が必要です。
ここで、初めのお話である「贈与税が高い」というのは、正しくない場合があります。なぜなら、相続税を概算で計算を行ったときに、相続財産の金額によっては、高い税率が適用される部分があります。
その部分の財産は、相対的に(相続税より贈与税の税率が)低い部分の金額までであれば、贈与税は(相対的に)安いということになるのです。
このような対策を行うためにも、概算で相続税を計算し、どの程度の税率が適用されそうか把握することが必要になります。
相続対策はお早めに!!迷っているくらいなら実施した方がよいです。
浜松/相続・相続税対策/浜松市中区/税理士・公認会計士事務所トップページ
親族がなくなられたときに、預金等の残高や借入の有無などを調べるために銀行から残高証明書を取ります。その際に必要な書類としては以下のものがあります。通帳があるから大丈夫と考えられる方もいらっしゃいますが、金融機関での残高を網羅的に把握するためにも取得することをおすすめします。
※あくまでも参考です。銀行等によって異なる場合がありますのでご確認ください。
- 除籍謄本
- 窓口に行った人の実印及び印鑑証明
- 免許証(本人確認のため)
浜松/税理士/相続税の申告/相続/疋田会計事務所
疋田税理士事務所(浜松市中区)に対して相続に関連して亡くなれた方に関する手続での質問があります。
亡くなられた方の金融機関貸金庫を確認したい
亡くなられた方の固定資産税に関する疑問
税理士/浜松市中区/相続税の申告/相続手続/疋田会計事務所/浜松
ケースとしては少ないですが、長生きされる方が多いこともあり、遺産分割協議書を作成する前(遺産分割協議中)に相続人の方が亡くなられてしまうケースがあります。
亡くなられた方が被相続人の配偶者の場合であれば、結果としてお子さんで遺産分割協議を行えばよいことになるのですが、相続人であるお子さんが亡くなられた場合には、少しややこしくなります。
つまり、そのお子さんの相続人の方が遺産分割協議に参加することになるため、協議に参加する方に変更が生じます。
また、集める書類も増加することになります。(亡くなられた相続人の方についても被相続人と同様の書類を集める必要があるのと、その亡くなられた相続人の方の相続人の書類を集める必要があります。)
遺産分割協議書に署名をする人も増加します。(亡くなられた相続人の方の相続人として署名することになります。)
遺産分割協議書作成については、行政書士、司法書士、税理士にご相談ください。
子どもがいない方の相続対策
相続税の申告・相続対策
遺言書作成から始まる相続対策
浜松/税理士/相続税の申告/疋田会計事務所
海外に相続人の方がいる場合 浜松/税理士 疋田会計事務所
海外に相続人の方が住んでいる場合、印鑑証明をとることができません。
そのため、よく言われる方法として、現地の日本大使館でサイン証明をとることと、あとは在留証明をとる必要があります。しかし、たとえばお盆やお正月、その他の理由で日本にその方がいらっしゃる場合に、公証役場でサイン証明をとることができます。
ただ、あくまでサイン証明をとることができるということだけで、それを法務局・税務署が了承するかは別のようですので、あらかじめサイン証明をどのような形ですればよいか確認が必要ですが、大使館が遠い場合などこのような方法を検討されてもよいかもしれません。
浜松/会計事務所/相続・相続税の申告/税理士・公認会計士
確定日付ってしっていますか?
みなさんは「確定日付」という言葉を聞いたことがありますでしょうか。
確定日付とは、変更のできない確定した日付のことをいいます。つまり、その日にその文書が存在していたことを証明するために用いられます。
契約書の中にはいつまでにその契約書が作られたかが重要なものがあります。(たとえば、税務関係ですと相続に関係してくるものは日付が重要になります。)
なぜなら。私人で作成した契約書に日付がを入れておいたとしても、実際には契約書に記載されている日付より後に契約書を作成したにもかかわらず日付だけさかのぼって書かれている可能性があるからです。
赤の他人の第三者であれば、それ以外の人には、その日付にあったということは信じてもらえるかもしえません。でも、贈与のように親戚同士での契約は、意図的に日付が操作できるとみられてしまいます。
贈与がいつ行われたかによって、相続税が変わってくる場合がありますから、贈与を行う際には公証役場で確定日付を付与してもらうことが望ましいです。
どのような処理をしてくれるのですか?
確定日付の付与は、具体的には公証役場に持っていった日付けが入ったスタンプ(印章-確定日付印)を書類に押してくれます。
このため、これはその日にその契約書が存在したということを証明するものであり、言い換えればその日より後に作成されたものではない、ということを証明するものです。
確定日付は契約書の作成者・契約の当事者が持っていかなくても付与してもらえます。ただ、契約書などは完成されたものでなければ付与してもらえず、日付や署名(または記名押印)されていないもの・違法な契約書などには付与してもらえません。また契約書の中身が適正であることを証明するものでもありません。
税理士/浜松/会社設立・起業/相続・事業承継/会計士・税理士事務所
相続で利用者識別番号を取得していない非居住者の方の申告を電子申告したい場合
相続で、税理士を納税管理人にしている場合には、非居住者の方の申告を電子申告でおこなえるようです。
ここで、疑問に思うのが、「長期にわたって海外で生活をしているため利用者識別番号を取得したことがなく、海外に移る前の住所といえるものがない場合はどうしたらよいか?」です。
なお、_1 ※「開始届出書(個人の方用)新規」をクリックし、『マイナンバーカードをお持ちでない方はこちら』をクリックし、画面の案内に沿って、手続き願います。
納税管理人の利用者識別番号を使用すればよい?
財産取得者(相続人)の利用者識別番号を使用してくだい。
相続税申告に当たっては、納税管理人の利用者識別番号ではなく、財産取得者(相続人)である非居住者本人の利用者識別番号を使用することとなります。
非居住者の利用者識別番号はどう取得したらよい?
開始届を提出してください
非居住者の利用者識別番号を取得する際は、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」(以下「開始届」といいます。)を提出していただく必要がございます。
開始届は、e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーからご提出ください。 ・(e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー)作成・送信する開始(変更等)届出書の選択 ⇒ https://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/kaishi3.htm#tabs
納税地や住所はどうしたらいいの?
納税地は国内の納税地を海外の居住地や納税管理人の情報なども記載してください。(税務署の方がわかるように)
開始届の提出に当たっては、「納税地」欄には、日本国内における納税地を入力していただき、ビル名等がある場合は、「丁目・番地」欄に入力してください。 また、海外の居住地を「建物名・号室」欄に記載していただくとともに、納税管理人の住所・氏名を「参考事項等」欄に記載してください。
相続が発生すると、その数ヵ月後に被相続人の親族などに「相続についてのお尋ね」と題した書面が届くことがあります。
税務署からそのような書類が届くということは、相続税がかかる可能性があると考えるべきです。なぜなら、税務署が人の死亡や死亡した人の親族関係を把握することは容易です。また、被相続人の所有不動産から、おおよその遺産は把握できますし、預金の金額も知ろうとすれば知ることができます。
相続税を納めるべきところ、納めていない場合には、延滞税や場合によっては無申告加算税がかかりますのでできるだけ早急にかつ慎重に対応をしていただきたいものです。
ところで、このような事態はなぜ起こってしまうのでしょうか?
- 相続財産について網羅的に把握していない。
・かからないとはじめから決めつけてしまう。
・ゴルフ会員権、有価証券、保険などが漏れていることが多い。 - 税制についての理解が不十分
・生命保険について非課税だと思っていたが、実際に非課税にならないケース
・相続したものを売却し、所得税を納めたので相続税はかからないと思ってしまうケース - 相続税の申告書が届いていない場合
・相続税の申告書が届いていない場合=申告しなくてよい場合と勝手に勘違いするケース
相続税については、専門家に相談しつつ慎重に対応することをおすすめいたします。
「相続についてのお尋ね」浜松の税理士関連記事
浜松/相続税の申告/浜松市中区の疋田会計事務所/相続についてのお尋ね
今回は、成年後見制度と相続税対策について説明をしたいと思います。
財産が相続税がかかるほどある方で本人が認知症になってしまい公正証書遺言も作れないという方が考えられることで、後見人を選んでそれにより相続対策ができるのではと思われる方がいらっしゃいます。
たとえば、毎年、子供や孫に110万円ずつ贈与していくことを後見人を選んでやろうということです。
しかし、それは現実には難しいです。後見人は、本人の財産を管理しなければなりません。たとえ、相続対策が認知症になる以前の本人の意思であろうと、難しいです。
この点に注意が必要です。
つまり、後見制度を利用しようかどうか検討していて、相続対策をしようと思われる方は、相続対策ができるかどうかは、本人の判断能力がどの位あるかという点が重要となるという点を理解しておいてください。
たとえば、判断能力の衰えがまだ浅い(例えば補助類型程度)であれば、後見制度を利用したとしても本人の残存能力の範囲内で法律行為は可能ということになります。つまり、このような場合であれば、遺言書を書くという点の相続対策は可能な場合があります。生命保険契約を契約することによる対策ができる場合もあります。
しかし、この場合でも、結局は贈与による相続税の対策などは先ほど難しいです。利益が相反するためです。
「後見人をつけるほどの判断能力であれば、対策は難しい」という点を理解しておいてください。
浜松市/成年後見制度と相続対策/税理士
相続でもめているケースについて
相続でもめているケースが近年増えています。もめている理由としては、兄弟間のコミュニケーション不足や以前は長男が相続をするという価値感だったのが変化していること、子供によって財産の状況がかなり異なることなど様々な理由があると思います。
しかし、相続税の申告期限は10ヶ月後にやってきます。期限内に申告がされていない場合には、無申告、期限後申告になってしまいます。
もめている場合には、下記のような問題が生じます。
- 相続財産の全貌がつかめない
- 遺産分割の協議がまとまらない
よくあるご質問
ここでは相続でもめている場合によくあるご質問をご紹介します。
相続がまとまっていない場合は期限後でもよい?
期限内に申告をしてください
相続がまとまっていない場合でも、預金や不動産の総額はある程度把握することが可能です。可能な限り部分だけでも良いので申告をしましょう。
遺産分割がまとまっていない場合はどうしたらよい?
分割できていない(未分割)ときは、法定相続分の割合で申告してください
遺産分割協議が整えば、その割合で申告をすることになりますが、整っていない場合は、法定相続分の割合で申告をしましょう。
相続税の申告書は連名になっているけど別々でよい?
別々に提出、税理士も別でかまいません。
通常相続税の申告業務は、相続人全員で一人の税理士に依頼して申告書を作成します。そこで作成された申告書に対して相続人全員で押印したうえで税務署に申告することとなります。
ところが、もめている場合のように同一の相続に対して税理士が複数存在し、それぞれ別の申告書を作成し税務署に提出するケースがあります。
このような場合は、別々に提出することになります。当然、税理士が違うことも認められます。
相続税の申告書の提出先は?
被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。
相続税の申告書の提出先は、納税地の税務署に提出することとされています。納税地とは相続税の条文の本則によると、「相続人の住所地」とされています。
しかし、実際には「被相続人の住所地」が納税地とされ、申告書が提出されています。これは、もともと相続税法では納税地を「相続人の住所地」として定めていたのですが、昭和25年の改正により、当分の間、納税地を「被相続人の住所地」とする附則が定められたことによります。
今でもこの附則は効果を持っていますので、相続人が共同して一つの同じ申告書を提出する場合も、相続人がそれぞれ別々の申告書を提出する場合も、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出することになります。
相続でもめている状況は理解できますが、なかなか進まない場合は、期限内申告ができるように税理士、弁護士、司法書士、行政書士など各種専門家の協力のもと行ってみてはいかがでしょうか。
疋田税理士事務所(浜松市/税理士) へのご相談はこちらをクリック
お問合せはこちら
税理士法人Compathy(コンパシー)のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください
お問合せはこちら

当事務所へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。
お電話でのお問合せ
053-476-1481
受付時間:8:30~17:30
(土日祝を除く)
お気軽にご相談ください。