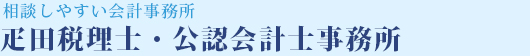会社設立、起業・開業する創業者の成長をサポート。気軽に相談できる若い税理士をお探しなら、浜松の税理士法人Compathy(コンパシー)にお任せください。
受付時間 | 8:30~17:30 |
|---|
アクセス | 助信駅より北に徒歩5分 |
|---|
事業承継について /浜松 税理士
事業承継対策
事業承継とは、会社(個人事業主であれば事業)を現在の経営者から、他の人(後継者)に引き継ぐ形で譲渡することを指します。
(1)会社組織と個人事業の比較
- 会社組織の場合
会社組織であれば社長交代が事業承継となります。つまり、代表取締役が変更されることで、経営は引き継がれることになるのです。
(同族会社のケースでは、社長交代の問題とともに株をだれに引き継がせるかという法人の所有という問題も同時につきまといます。株式会社形態をとれば、所有と経営が分離しているのが原則なのでそれを前提に解説します。)
- 個人事業の場合
個人事業の場合には実際は息子がきりもりしていたとしてもあくまで事業主は父親です。そして、法人のように事業を所有している人と経営している人の分離ということもないですから、事業主が経営者ということになります。
なお、個人事業の場合は、財産の移転という問題が生じます。財産の移転は、一般的に相続によった方が税務上のメリットが大きいため、死亡によって相続と同時に事業を承継するケースが多いのが現状です。
続きを読む
税理士/浜松市/疋田会計事務所/相続税・事業承継
消費税の損金の計上時期については以下のように消費税の経理処理により異なっています。
(1)税込経理
課税期間の終了とともに、納付又は還付を受ける消費税額を計算します。そのため、以下のようになっています。
| 区分 | 計上時期 | |
|---|---|---|
| 納付すべき消費税等 | 還付を受ける消費税等 | |
| 原則 | 納税申告書の提出日 | |
| 更正・決定 | その更正又は決定の日 | |
| 特例 | 未払金に計上したときは、その計上した日 | 未収入金に計上したときは、その計上した日 |
(2)税抜経理方式
課税期間の終了のときにおける仮受消費税等の金額から仮払消費税等を控除した金額の差額が納付する又は還付される消費税に原則としてなりますので、所得税(法人のときは法人税になります。)の額に影響を与えません。
簡易課税制度の適用を受けたり、上記差額と納付額(還付額)と一致しないときは差額の調整も課税期間を含む事業年度に処理をします。
続きを読む(事業承継時の注意点)
税理士事務所/浜松市中区/相続・事業承継
法人の事業承継 /税理士 浜松
法人の事業承継については以下の問題があります。
- 代表取締役をだれにするか
- 法律上の会社の所有者をだれにするか
※(2)は、「会社は誰のものか?」という議論がリーマンショック以降様々なところでなされており、考え方もいろいろです。そこで、法律上としました。
中小企業では、同族会社が多く、それほど株式が分散していないこともあり代表取締役をだれにするかという問題と株式をだれに譲るかという問題を切り離して考えている方がいらっしゃいます。
「いやいや、そんなことはないよ」とお話される人も多いのですが、具体的には、代表取締役は、後継者としてふさわしい長男を選任すればよい、株式は、税金が安くなるように息子や時には従業員に渡すと考えている方がいらっしゃいます。
しかし、私は株式はできるだけ分散させないようにとお話するようにしています。
株式を分散させて、税金がやすくなっても、株主が権利を行使して役員を解任させられたりすることで会社が混乱しては元も子もないです。
それなので、株式を引き渡す相手は慎重に考えてください。
また、税金をできるだけ安くしたいと考えられている人は、できるだけ早く対応するようにしてください。
事業承継などについてお悩みの方は浜松の疋田会計事務所までご相談ください。
今回は抽象的な内容を書きましたが、具体的な話をまた別のときに書きたいと思います。
税理士事務所/浜松市中区/事業承継・相続/後継者支援トップページ
事業承継について、少しずつですが解説を行いたいと思います。
中小企業の動向を知るための資料としては『中小企業白書』が挙げられると思います。
浜松市は、中小企業白書でも例としてあげられるほど、中小企業の多い町です。
近年、経営者の高年齢化が進み、廃業する件数が増えています。
浜松市・湖西市において、雇用が維持され、発展していくためには、事業の存続が必要であり、そのためには事業承継が重要と考えられます。
経営の実態と経営者
経営者が高齢化すると、実質的に息子が経営者としての役割を果たすようになります。そのようになった場合には、実態に合うように、経営者を息子にするというのが良いと思います。
それでは。経営者を後継者である息子に引き継ぐにはどのようにすればよいでしょうか。
今回は、個人事業のケースについて説明をしたいと思います。
続きを読む
個人の事業承継での悩ましい点(浜松市の疋田税理士)
税理士事務所/浜松市中区/事業承継・相続/後継者支援
遺言書の重要性は、「遺言書作成からはじまる相続対策」「遺言書作成からはじまる事業承継対策」のところで書かせていただきました。では、遺言書を作成するとしたときどのようにみなさんは作成されるでしょうか。
遺言には、民法で定められた一定の方式があり、これに従わなければ遺言は無効となります。
ここでは、まず遺言書の種類(方式)について説明をさせていただきますと、遺言の方式は、大きく分けて2つに分かれます。
- 普通方式
- 特別方式
普通方式の遺言は通常のケースであり、特別方式の遺言は普通方式の遺言ができないという特別な事情の場合に認められるもので、基本的には通常の方式によらなければならないことになります。
(ちなみに、特別方式は重病で死期が差し迫っている危急な場合や、船舶に乗船中であるといった場合などです。)
普通方式の遺言の種類
普通方式の遺言には以下の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれなんとなくですが聞いたことがあるかもしれません。全く聞いたことがない人は、遺言というと(1)の自筆証書遺言をイメージされることが多いと思います。
3つの方式は、作成方法が異なり、長所・短所があります。それなので、長所・短所について充分に理解して遺言書作成手続を行う必要があります。
遺言書作成にあたっては、司法書士・弁護士・行政書士・税理士など各種専門家に相談されるのもよいでしょう。
税理士/浜松市中区/相続税の申告/相続手続/疋田会計事務所トップページ
株式を贈与することを考えると、時価がいくらかが問題になります。
所得税法の時価は?
所得税法上には、非上場株式の評価方法について直接定めた規定はありません。
所得税法施行令84条に非上場株式の価額を算出する必要がある場合に、非上場株式の価額、すなわち時価とは何かを定める通達です。
そして、その株式の価額を求める通達として所得税基本通達があります。
原則的評価方法は、この所得税基本通達の23条〜35条共-9によることとなります。
実務上の評価方法は?
ただ、問題は、これでは実際に評価することは難しいです。
そのため、平成12年になり、所得税基本通達59-6が出され、これにより評価することとなりました。
※ちなみに同通達は、法人税基本通達9-1-14とほぼ同じ内容となっています。
- 同族株主に該当するかどうかは、贈与等した個人の贈与等の直前の保有株式数で判定する。
- 当該個人が、「中心的な同族株主」である時は、当該会社は「小会社」に該当するものとされます。
- 当該会社が、土地等及び上場有価証券を保有している時は、純資産価額の算出にあたって譲渡等の時における時価による。
- 純資産価額方式の計算に当り、評価差益に対する法人税額等相当額の控除をしない。
中小企業の事業承継では、おそらく、中心的な同族株主からの贈与を検討されると思います。算定に当たってはこれらの事項について注意が必要となります。
浜松市中区/税理士/浜松の疋田会計事務所/相続・事業承継トップページ
他の業界でもそうですが、法人をつくり、社会のために仕事に励んできた方が高齢化し、中には亡くなられる方がでてきたため相続や事業承継の問題が生じています。
医療法人では、独特の業界であるため、特に問題を複雑化させています。
- 医師の子供がかならずしも医師とはかぎらない。医師でなければできない。
- 医師だとしても医療法人を継いでくれるとはかぎらない。(これは他の業種でもあります。)
- 近年、医療に関する様々な法律が改正されている。
簡単に説明をさせていただくと、このようなことでしょうか・・・・。
「相続や事業承継にあたって、問題が生じそうだな・・・。」となんとなく感じていただけると思います。
そして、医療法人は、長年の積み重ねで剰余金が多額となっているケースがあり、出資持分のある医療法人の出資社員が死亡した場合に、相続人に対して相続税が課税される場合は、医療法人の財産状態などによっては、その納税額が巨額に上ることもあるのです。
また、それならということで、出資持分について払戻請求を考えた場合、払戻額が高額になります。その結果、医療法人の存続そのものが脅かされる事態が生じるといわれています。
出資者の考え方からすると、出資持分を払戻し請求することができることとなりますが、多くの方はその医療法人の存続を第一に考え、出資持分の払戻しにより、医療法人の経営を圧迫したくないと思っています。
しかし、医療法人経営に直接関与していない出資者あるいは医療法人経営等をめぐる意見の対立により退社した出資者から、出資持分の払戻請求権を行使されることがあるようです。兄弟間での意見対立や共同経営者間の意見対立などが見られます。とりわけ、兄弟間での意見対立は、親という仲介者がいる場合には決定的な対立にはならなくても、親が他界した後では、深刻な対立になる場合が多いようです。
このように医療法人を経営されている方は、早期の事業承継対策が必要になります。
とりあえずは、どのような点から検討していかなくてはいけないか。顧問税理士にご相談されてはいかがでしょうか。
医療法人の事業承継についてお悩みの方、創業者の方、後継者の方、どなたでもお気軽にご相談いただけたらと思います。
医療法人/浜松/税理士・公認会計士/事業承継
お問合せはこちら
税理士法人Compathy(コンパシー)のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください
お問合せはこちら

当事務所へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。
お電話でのお問合せ
053-476-1481
受付時間:8:30~17:30
(土日祝を除く)
お気軽にご相談ください。